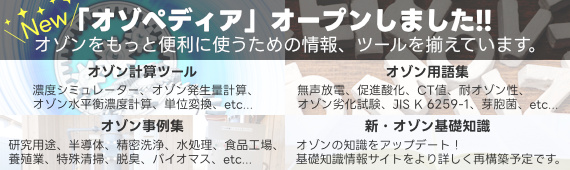皆様お元気ですか、エコデザインの長倉正弥です。
立川眞理子先生へのインタビュー、後編をお届けします!
(インタビュー日:2019年11月26日)
目次
立川眞理子先生のご紹介

立川 眞理子(たちかわ・まりこ):日本大学理工学部薬学科 卒業後、同大学薬学部 教授(定年退職)。博士(薬学)。専門は衛生化学、水環境。特に塩素剤やオゾンによる殺菌や、バイオフィルムの除去性について研究を行う。メディア出演歴あり(NHK総合『チコちゃんに叱られる!』など)。塩素フェチ。
〈インタビューの前編はこちら〉
 【インタビュー】立川眞理子 先生(元 日本大学教授)〈前編〉——環境に興味が湧いたら、まずは勉強から始めてみてください
【インタビュー】立川眞理子 先生(元 日本大学教授)〈前編〉——環境に興味が湧いたら、まずは勉強から始めてみてください
塩素フェチ! 塩素が大好き!
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生でもその使い方とか特長というのが人によく伝わっていないことが多いと感じています。長い間塩素に携わってきたのに、ちょっとアピールが足りていなかったなと。それが反省ですね。
少しでも「塩素は○○なんだよ」ってことを分かってほしい。それが今の私のスタンスです。

オゾンも扱い始めて良かった
 立川先生
立川先生2つを対比させて考えてやることで、オゾンと塩素それぞれの良いところが見えてきたんです。
塩素は手軽だしどこでも使えますが、上手く使うにはいくつかの配慮が求められます。一方、オゾンはオゾン発生のための装置が必要になりますが、小規模なプラントなどでの水処理に用いるのにすごく適した小さな製品がどんどん出来てきていますよね。それこそエコデザインの製品とか。
今の水処理というのは、流域下水道のような大きな単位での処理よりも、その場その場で適切な処理を行いましょうという小さな単位の考え方に転換してきていると思うんです。それに適応できる技術として、オゾンの良さを活かせるんじゃないかと。
私がオゾンに初めて触れたころというのは、オゾン発生器といえばとても大型で。東京都水道局で使われるような巨大なものしかイメージできませんでしたからね。
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生
クロラミンを作るだけじゃなくて「バイオフィルムも自分で作る」
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生バイオフィルムというのは、スライムとも呼ばれ、微生物が作りだす集合体なんです。排水口とかに付着するぬめりと言えばわかりやすいかもしれませんね。環境中の微生物の住まいなんです。
一般に、細菌というのは空気中にフワフワ浮遊しているものだと思われていますが、実際には環境中の細菌の殆どはバイオフィルムとして何かに付着し、そこで生活圏を作っているんです。
だから、本当に菌を根絶やしにしたいならば、バイオフィルムを叩かなければなりません。
水槽の水だけを殺菌しても、時間が経てば菌数はすぐに戻ってきてしまう。それでは水槽のバイオフィルムを除去できていないということなんですね。
バイオフィルムを取り除く目的のためには、手段となる様々な塩素剤がバイオフィルムにどのように作用するのか、巣に本当に効いているのかを調べたかったんですよね。
そこで、私はバイオフィルムを自分で作ることにしました。

 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生バイオフィルムを取り扱う上で、注意しなければならないことがあります。調べたいバイオフィルムを見つけても、その場から引き剥がしてしまうと、もうそれは「バイオフィルムではなくなってしまう」ということです。
多くの場合、バイオフィルムはその成分の9割以上が水なんです。残りが、菌体と、菌体から出される様々な成分です。
引き剥がしてしまうと、水分もなくなってしまうし、元々のバイオフィルムの構造が失われてしまいます。それでは、バイオフィルムの正しいすがたを見ていることにならないんです。
だから、自分でバイオフィルムを作ろうと。
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生オゾンでの実験の始まり
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生当時はオゾン発生器といえば大型のものばかりで、一研究者が取り扱うには難しいと思っていましたが、中室先生が小型のオゾン水の手洗い器を借りてくださったので、そのオゾン水を使って実験を始めることができたんです。
 長倉正弥
長倉正弥
持続可能な社会に向けて、期待すること
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生そこで注意しなくてはならないのが、適正な使用法です。
過剰な添加にならないかといったことや、消毒副生成物への配慮が必要だと思います。
適切な量・適切な使用方法も考えなければなりませんし。
塩素とオゾンで、お互いに得意な分野、不得意な分野を補完し合いたいですね。
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生個人の力だけでは、無理なことが多いでしょう。
 長倉正弥
長倉正弥
『チコちゃん』に出て伝えたかったこと:環境とは
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生みんな、プールの中に浮遊物があったり汚れていたりすると「うわ、汚い」と言って避けようとしますよね。でもプールの汚れというのは、自分たちが出したものであって…。
自分が原因なんだよということを、分かってほしかったんです。なので、出ちゃいました。
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生皆さんには、「環境というのは自分自身の周囲にただ存在するものではなくて、自分自身も含んでいるものなのだ」という捉え方でもって、環境について考えてほしいですね。
塩素だってそうなんですよ。塩素だけが悪者なのではなくて、環境(水)中に溶けている汚れ成分が、塩素との反応により影響を及ぼしているのだとね。
 長倉正弥
長倉正弥

 立川先生
立川先生 長倉正弥
長倉正弥
これからも、塩素フェチならではの話を
 長倉正弥
長倉正弥
 立川先生
立川先生 長倉正弥
長倉正弥
インタビュアーのひとこと
立川眞理子先生は、塩素の専門家として知られています。その根底には人々が病気にならないよう未然に防ぐ、衛生的な考えがあることが今回よく分かりました。
バイオフィルムは剥がしたらもうバイオフィルムではなくなっているということや、それならバイオフィルムを自分で作ろうという話、「一般人が環境に興味を持ったらまずは勉強」という教えなど、衛生化学の研究の第一線にいらっしゃったからこそのお話を聞けたように思います。とても面白かったです。

このたびは、本当にありがとうございました!
(インタビュー内容は取材当時のものです。所属、業務内容などは現在では変更となっている場合があります。)
〈立川先生の連載記事はこちら〉
 クロラミンについて知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #5】
クロラミンについて知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #5】
 水中の有効塩素濃度(残留塩素)の測定について知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #4】
水中の有効塩素濃度(残留塩素)の測定について知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #4】
 塩素剤で確実な殺菌作用を得るためには? 水のpHと塩素の関係を知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #3】
塩素剤で確実な殺菌作用を得るためには? 水のpHと塩素の関係を知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #3】
 残留塩素の意義は? 不連続点処理って? 水の消毒を知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #2】
残留塩素の意義は? 不連続点処理って? 水の消毒を知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #2】
 塩素の殺菌作用は? 次亜塩素酸ナトリウムって? 塩素を知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #1】
塩素の殺菌作用は? 次亜塩素酸ナトリウムって? 塩素を知ろう【塩素マニア・立川眞理子の連載 #1】
(2022年5月9日:立川先生の連載記事 第4回・第5回へのリンクを追加しました。)
(2020年10月1日:オゾン・塩素初心者向けマークを記事に付与しました。)
(2020年8月18日:立川先生の連載記事 第3回へのリンクを追加しました。)
(2020年7月7日:立川先生の連載記事 第2回へのリンクを追加しました。)
(2020年6月17日:立川先生の連載記事 第1回へのリンクを追加しました。)