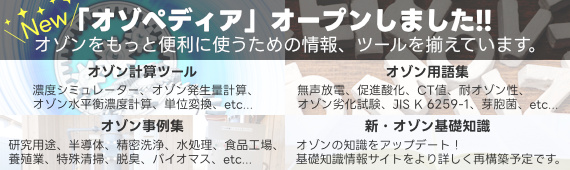目次
はじめに -オゾンと環境消毒-
はじめまして、杉光英俊(*)です。エコデザインさんから、オゾンについての連載のお話をいただきました。何年も現場から離れており、難しいことはお断りしようと思っていましたが、新型コロナウイルスが猛威を振るう中で消毒薬が不足しているのを見て、気がかわりました。バクテリア、ウイルス、原虫まで死滅させる力をもち、環境にも優しいオゾンがもっと利用されるべきだと思うからです。
(*)第7代徳山大学学長(2001年~2010年)。理学博士。
かつてヨーロッパではオゾンは「健康」のシンボルであり、オゾンによる浄水は近代ヨーロッパを象徴するものでした。
しかし、世界の主流になっているのは塩素です。短時間に分解して保存ができないオゾンは取り扱いが難しく、経済的でもなかったからです。
しかし、時代はかわりつつあります。オゾンの原料は空気や水です。なので原料が不足する心配はありません。電気さえあれば質の高い環境消毒剤の利用が可能になったのです。
この連載では、消毒剤としてばかりでなく、上下水から環境親水処理、農工業、医療分野まで、さまざまに活躍の場を広げているオゾンとその基礎となる応用技術、安全性についてわかりやすく紹介していきたいと思います。
オゾンの殺菌作用はどこから?
オゾンは酸素O2の同素体で、分子式はO3です。
空気中に含まれる単体としては最も酸化力が強く、オゾンの殺菌作用はこの強力な酸化力によるものです。
バクテリアやウイルスなどの生命体は有機物で構成されています。オゾンは生命体を構成する有機物を酸化し、破壊することによって不活化します。
生命体が小さいほど大きなダメージを与えますので、ウイルスに対する消毒剤としてオゾンは最適であると考えます。
特定の機能に対する作用ではないため、適用対象が広く、これからも出現すると思われる新種のウイルスの薬剤耐性の獲得や薬剤耐性菌の発生も原理的に心配する必要がないと考えられます。
1998年に発行された医療関係者向けの「消毒,滅菌ガイド」では、オゾン滅菌の特徴として、「滅菌に要する時間が短かく、後処理が不要なこと」、問題点として、「ガスとして保存が効かない、浸透性が低い、ゴム製品を腐食する」などがあげられていますi)。
毒性や発がん性を懸念する記述もありますが、医療機器滅菌用として1989年にFDAより認可を受けており、手術室、ベッド、マットなどの環境消毒用としての開発も進められていますi)。もちろん日本でもすでにいくつかの医療機器が厚生労働省の認可を得ています。
2009年の研究ではヒトに対する発がん性は否定されていますii)。オゾンの毒性や腐食性等については今後、処理対象ごとに触れていくつもりです。
オゾンはどこにある?
オゾンは大気中に含まれている自然物です。高度10km以上にある成層圏には高濃度のオゾン層があります。これは、酸素分子が強い紫外線を受けて解離し、酸素と再結合して生じたものです(R1, R2)。
成層圏のオゾンは紫外線を吸収して地上の生命を保護し(R3)、温室効果ガスとして地表大気の温度を保つ役割を担っていますiii)。
- 【R1】 O2 + 紫外線(波長240nm) → O + O
- 【R2】 O + O2 + M → O3 + M
- 【R3】 O3 + 紫外線(波長320nm) → O2 + O
- 式中のMは反応の第三体で、空気中では窒素と酸素です。第三体とは、結合反応において余分なエネルギーを吸収する物質のことを指します。
100年前に出版された自然科学の事典では地表オゾンについて次のように記載されています。
大気中には常に多少のオゾンが含まれている。量は時と場所で異なり、春は最も多く、季節が進むにつれて減少する。海浜で最も多く、都会地は最も少ない。海浜地が病弱者等の転地に適するのはオゾンが多量に含まれているため空気が清潔なことによる。都会地に少ないのは、酸化作用の強いオゾンが市街地に浮遊している塵埃や有機物で消費されるからであろう。iv)
ここで注目されるのは、今はオゾンが海浜地よりも都会地で多いことです。この光化学オキシダントとオゾンの関係については後の章で述べます。
使われたオゾンはどうなる?
オゾン利用の最大の利点は、後処理の必要がないことです。反応しなかったオゾンは時間をかければ自然に分解して酸素になります。過剰に利用する場合は触媒などで分解処理することができます。
これはオゾンを環境消毒剤として使用する上で重要なポイントになります。
塩素による浄水処理の場合には水質が悪化すると消毒剤が多くなったり、副生物の毒性が懸念されますが、オゾンの場合の生成物は酸素化合物ですので問題は少なく、副生物によって健康に問題が生じた例は聞きません。
オゾン処理後の水質の安全性は、下水処理場の排水が公園の親水用水として利用されていることでもわかります。
浄水処理の最終段での塩素の添加は、配水途中での万一の汚染の可能性に備えるためです。
持続力がないオゾンと少量で消毒効果が持続する塩素の組み合わせは、ベストマッチングといえます。

オゾンは臭うからこそ安全
都市ガスには着臭剤が加えられています。本来は無臭なので、着臭剤を加えておかなければ、ガス漏れに気づけない可能性があるからです。
一方オゾンは、オゾン自体が臭うのでその必要がありません。
オゾンの発見者であるシェーンバインは、ギリシャ語の “臭う”からオゾンと命名しました。オゾンのにおいは0.02ppmくらいから感知でき、労働安全基準値の0.1ppm以上では刈りたての牧草のにおい、それ以上では強烈なにんにくのようなにおいがするとされていますv)。
実際のにおいの感じ方には個人差があり、魚のような生臭いにおいという人もいますし、スイカのにおいに似ているという人もいます。
どちらにしても、オゾンはこのにおいのおかげで、中毒するほど吸引する心配はなく、致死的な事故の報告は見たことがありません。
オゾンは冤罪?
1970年7月には光化学スモッグ事件が起きました。東京の杉並区の高校で運動中の生徒43名が次々に目や喉の痛み、咳き込み、手足のしびれ、呼吸困難などを訴え、病院で診察を受けましたvi)。
都の公害研究所は、光化学スモッグによるオキシダントが原因だったと発表しましたvii)。オキシダントとは、オゾンを含む酸化性物質の総称です。
ここまではいいのですが、「オキシダント=オゾンのこと」としている向きが多いのは問題だと考えています。
なぜならば、事件当時誰からも臭いを感知した報告がなく、オゾンでは考えられない強い刺激症状が見られていることからです。
もし人が倒れるだけのオゾンがあるならば、オゾン臭がしない状況というのは考えにくいのです。
オゾンとオキシダントは区別していただきたいと思います。

オキシダントとオゾン

※PAN:パーオキシアセチルナイトレート(CH3CO2NO3)
図は光化学オキシダントの発生機構ですviii)。通常のオゾンは図左側2列の反応だけですが、有機物が加わるとオキシダント(酸化性物質Ox)が大量に発生します。
定常的に観測される物質こそオゾンであっても、残り数百種類もの物質がその時々で変化するといわれていますvii)。
促進酸化処理(AOP)
オゾンで難分解性の有機物などを酸化分解するには、促進酸化処理AOP(Advanced Oxidation Processes)が利用されるようになってきました。その一つが紫外線の併用です。
オゾンを注入すると同時に紫外線でオゾンを光解離すると、より活性が高いヒドロキシルラジカル(OH)やヒドロペルオキシル(HO2)などの酸素活性種を生成し、これにより反応が加速されるのです(R4~R6)ix)。
- 【R4】 O3 + 紫外線(波長310nm) → O* + O2
- 【R5】 O* + H2O → 2OH
- 【R6】 OH + O3 → HO2 + O2
式中のO*は活性酸素原子です。
光化学オキシダントも、活性種を爆発的に発生させていると考えてよいのかもしれません。
オゾンとコレラパンデミック
19世紀のヨーロッパで猛威を振るったコレラパンデミック(世界的流行)は、当時のヨーロッパ諸国の膨張主義政策(植民地獲得競争)によるものといわれています。
病気の原因がわからないまま、上水道整備が先か、下水道が先かと議論された当時の都市政策論争は興味深いものです。
「不衛生は人の病気や死亡を誘発する、これは冨の源泉である人の損失に等しい。健康のために用いられる資金ほど利益を生む投資はない」と言う主張が支持を得て、下水道整備が急がれました。
当時、糞尿は街路に捨てられており、その“不衛生”を避けるために下水道が必要なことは確かでしたから、これ自体は立派な議論でした。
しかしながら、当時この下水道整備政策がパンデミックの撲滅に効果を上げることはできませんでした。
街路に捨てる代わりに下水を通じて河川に糞尿が投入されたのですが、飲料水に用いる井戸の多くは河川のそばにあったのですx)。
街路はきれいになりましたが、それで病気が抑止できなかったのは当然でした。コレラの原因は下水道ではなく上水道にあったということです。
原因と結果を取り違えると、全く予想しなかった災いを招きかねません。
その後の展開
コレラ菌が発見され、オゾンに殺菌力があることがわかると、フランスはすぐにオゾンを利用した公共水道の整備に乗り出し、それはヨーロッパ全土に広まりました。
戦後の一時期、アメリカ軍規則によって塩素消毒が導入されましたが、米軍撤収後はすぐにもとのオゾンにもどりました。
日本では戦後米軍規格の塩素消毒が全国で続いています。また、淀川、印旛沼などを水源とする地域から始まったオゾン浄水も、現在では東京都全域に配水されるまでになっています。
一冊の本との出会い
『オゾナイザハンドブック』電気学会オゾナイザ専門委員会〔編〕、コロナ社(1960年)を挙げさせてもらいました。
60年も前の発刊ですが、内容は今見ても遜色がなく得がたい逸品です。

私が上智大学に助手として採用され、鈴木桃太郎、岡崎幸子両先生のもとで「オゾナイザ中の化学反応」の研究を命じられた時に手渡されてから、終始手元に置いていたものです。
当時日本では大型のオゾン発生器はまだ製造されていませんでした。業界の要望を受けた電気学会は、専門委員会を設置しました。
委員長には高速化学反応の鈴木桃太郎先生(防衛大学校)、委員に高電圧工学の鳥山四男、気体放電現象の本多侃士、電気化学の杉野喜一郎、電力技術の法貴四郎、高電圧の幹事 内藤義英(都立大学)、竹村直(電気試験所)、幹事補 多田照子(電気試験所)など総員31名で構成され、3年以上にわたって審議されたものです。
本はすでに絶版になっていて、私も複写本を使用していました。写真は私が山口県の徳山大学に転任した折りに、広島市の古書店で偶然入手したものです。
📚 参考文献
- 小林寬伊〔編〕. 消毒,滅菌ガイド——感染制御のために. 中外医学社, (1998), pp. 121-122.
- NEDO 技術開発機構, 産総研化学物質リスク管理研究センター〔編〕, 中西準子, 篠崎裕哉, 井上和也〔著〕. オゾン——光化学オキシダント. 詳細リスク評価書シリーズ, 24. 丸善, (2009), p. 21.
- 島崎達夫. 成層圏オゾン. 東京大学出版会, (1979).
- 倉林源四郎, 大森乙五郎. 自然界之理化智嚢. 中興館, (1917), p. 142.
- 電気学会オゾナイザ専門委員会〔編〕. オゾナイザハンドブック. コロナ社, (1960), p. 269.
- 常俊義三. オキシダントの被害とその応急対策. 環境技術. 環境技術研究会, (1972), 1 (6), pp. 423-426.
- 山口勝三, 菊池立, 斉藤紘一. 環境の科学. 培風館, (1998), p. 35.
- L.T. プライド〔著〕, 岡本剛〔監訳〕. 新しい化学——生活環境と化学物質. 培風館, (1976), p. 101.
- 杉光英俊. 水環境におけるオゾンの利用状況. 水環境学会誌. 公益社団法人日本水環境学会, (1998), 21 (3), pp. 126-132.
- 見市雅俊, 高木勇夫, 柿本昭人, 南直人, 川越修. 青い恐怖 白い街——コレラ流行と近代ヨーロッパ. 平凡社, (1992).
(2020年10月1日:オゾン上級者向けマークを記事に付与しました。)
(2020年8月12日:絵文字が文字化けしていたため、修正しました。)